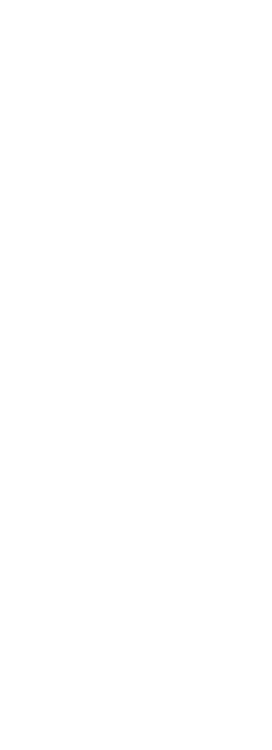弘法大師空海のご遺徳をしのび、御影堂での御影供(みえく)の法要に多くの人がお参りするようになりました。やがて、ご参拝する人々のために「一銭一服」の茶屋が店を開きました。
それから700年あまり。毎月21日、境内は1000店近くの露店で賑わい、弘法市として親しまれるようになりました。
賑やかな
「弘法さん」の法要

御影堂での法要
御影堂は、弘法大師信仰の発祥の地です。毎月21日午前10時から、弘法大師空海に報恩感謝する御影供という法要を御影堂で行います。また、弘法大師空海がご入定になった4月21日(旧暦の3月21日)には、正御影供(しょうみえく)の法要を行います。

講堂で読経する僧
この御影供は、延喜10年、910年に東寺の灌頂院(かんじょういん)ではじめられました。天福元年、1233年に仏師運慶の子、康勝(こうしょう)が弘法大師空海の尊像を刻み、延応2年、1240年からは御影堂でも御影供の法要を行うようになりました。

弘法市で賑わう境内をゆく僧
やがて、毎月21日の法要に人が集まり、茶屋が店を開くようになりました。団子や、薪や炭、鍋釜といった日用品も売られるようになり、700年以上の歳月を経て、いまのような賑やかな弘法市となりました。
いつしか、弘法大師空海は「弘法さん」と親しみを込めて呼ばれるようになり、21日は、弘法さんの日になりました。